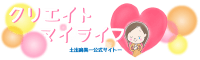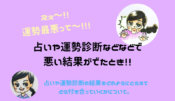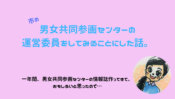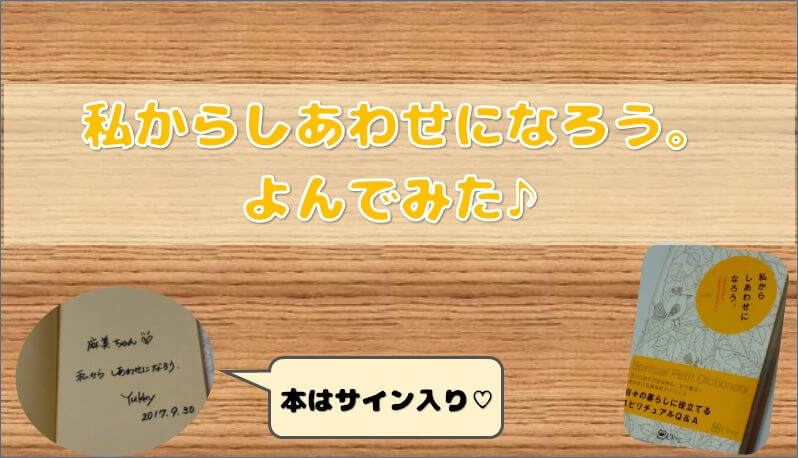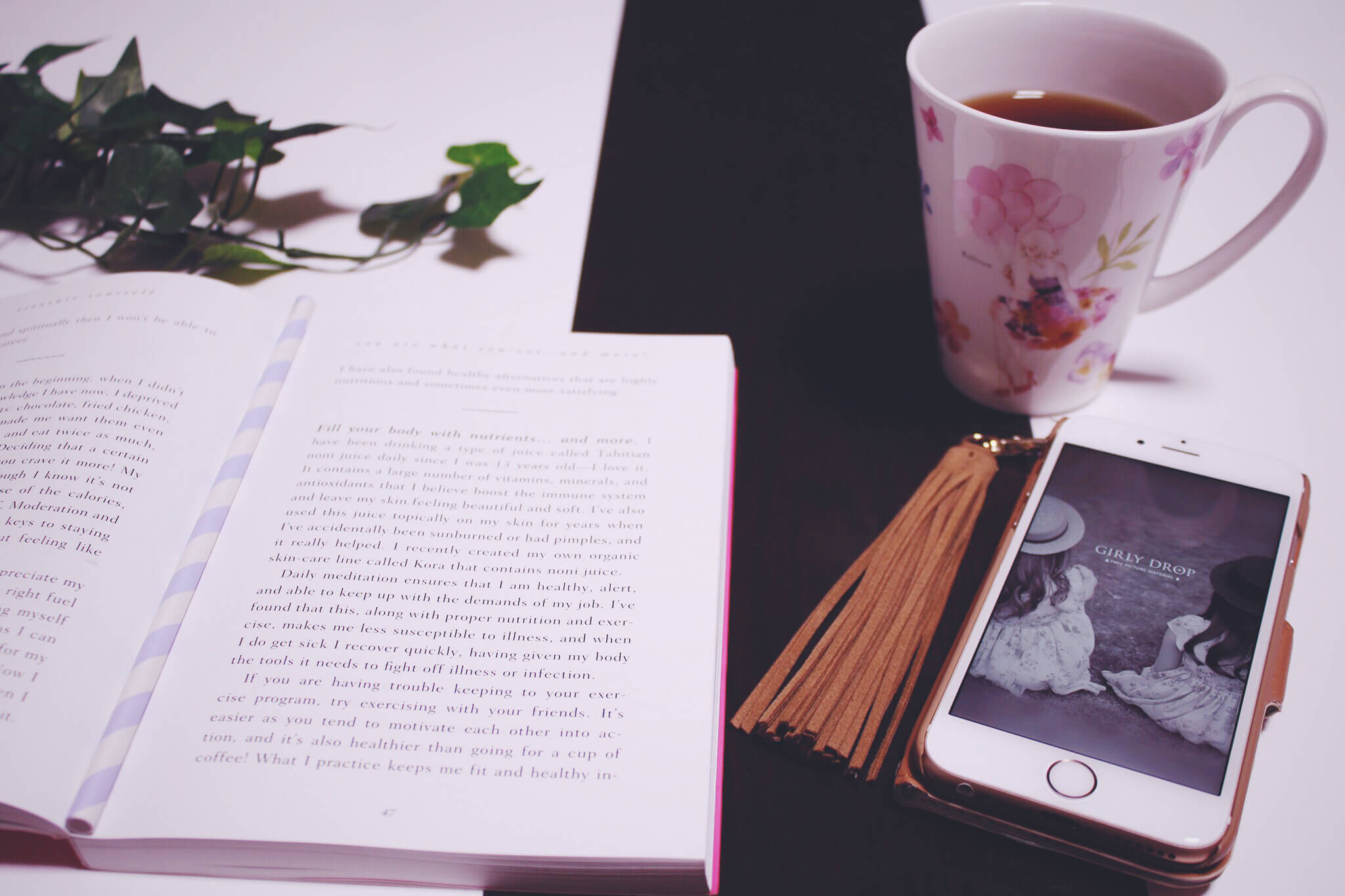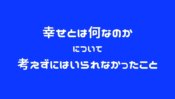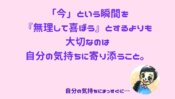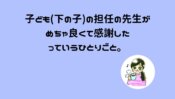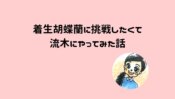子どもの心の成長に大切なものとは?「空が青いから白をえらんだのです」を読んで感じた、子どもの心に大切なものについて
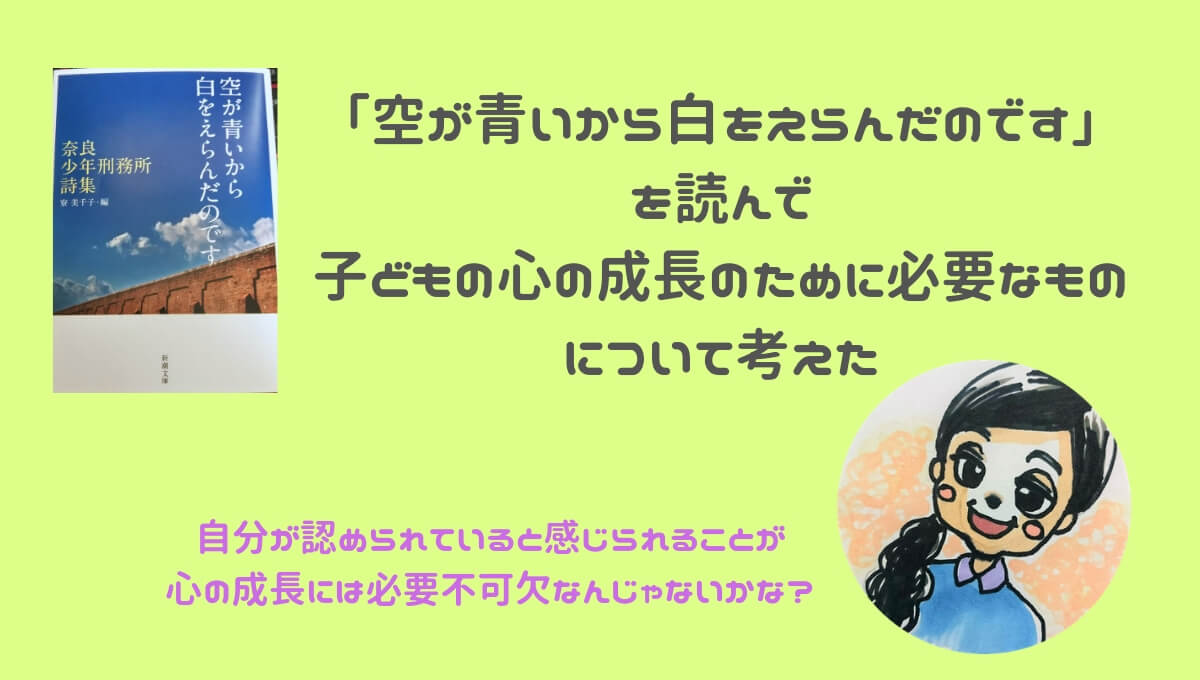
「空が青いから白をえらんだのです」というタイトルの本を読みました。
この本は、奈良少年刑務所の中にいる犯罪を起こしてしまった子どもたちが作った詩をまとめたものです。
「社会性涵養プログラム」というものの中で、子どもたちの情緒を育てるためにされた授業の中で生まれた詩。
 この授業をされていた寮美千子さんが詩をまとめ、社会性涵養プログラムについて書かれていて、詩は心をうつし出していて、社会性涵養プログラムについても興味深く、子どもの心を成長させるのに必要なことについてとても考えさせられました。
この授業をされていた寮美千子さんが詩をまとめ、社会性涵養プログラムについて書かれていて、詩は心をうつし出していて、社会性涵養プログラムについても興味深く、子どもの心を成長させるのに必要なことについてとても考えさせられました。
今回はそんな記事。
この記事の目次
「空が青いから白をえらんだのです」を読んで、その詩に涙せずにはいられなかった
この本を読みたいと思った理由は、タイトルにもなっているこの詩に圧倒的に心を惹かれたからです。
タイトルの「空が青いから白をえらんだのです」とは、「くも」というタイトルで少年が書いた詩。この言葉だけでも透き通るように美しく感じたけれど、ここに秘められている思いを知った時には言葉を失いました。
詳しくは本を読んでもらえれば良いと思うのだけれど、この詩を書いた少年はお母さんを亡くしているのですね。
亡くなる前に、「空を見たら私がいる」というようなことを伝えていたから。だから、この、白い雲はお母さんなんですね。
この、「空が青いから白をえらんだのです」という本は最初の3分の2ほどのページが少年の詩集(と寮美千子さんの解説)になっていて、後半の部分からは著者の寮美千子さんの社会性涵養プログラムについてや奈良少年刑務所についてのことなどが書かれています。
詩を書いた少年は、それぞれに重い犯罪を犯した子どもなのですが、みんなとても素直で美しい詩を書いているんです。
どれだけ正しい詩や文章を書くかではなく、どれだけ自分を表現できるかということが本当に大切だなぁと思いました。
とても素直に書かれた詩は本当に心を打つ。
とにかく詩集後半の母親に向けて書かれた詩は、涙なしでは読めませんでした。私が母親という立場の人間だからというのももちろんあるのだろうけれど。
どれだけ愛情を求めているんだろう。子どもにとって自分は無条件に愛される存在だと思えることは本当に大切なんだと。そう思ったのです。
そして、本当に母親という存在は大切なんだと。
 そう思わずにはいられなかった。
そう思わずにはいられなかった。
「お母さん」という心の叫びのように感じたから。
この世には子どもが欲しくてもなかなかできない人もいるでしょ?母親になりたいと思っているのになれない人。
母親がいてほしいのにいない子もいるんだって。そう思った。
「そりゃいるだろう」って、頭ではわかっていたけれど、心から思った。
母親になりたくてもなれない人、もちろん自分の赤ちゃんが欲しいんだろうけれど、母親が欲しい子の母親になるのはダメなのかな?とか思った。
自分のお腹から産む子と里子は違うのかもしれない。でも、もしかしたら、もっと里親制度とかそういった支援が広がれば、救われる子もいるのかもしれないと。
もしくは、私のような普通に子どもがいる人が、そういう子供を子どもとして迎え入れてみるとか…。
そう思ったのでした。
だけど想像してみたときに、自分の家に迎え入れるには難しそうなことばかりが思いついた。
金銭的な問題はもちろんのこと、普通の人はそういうの嫌がりそうだと思ったし、たとえ自分の子どもが大人になった後だとしても、難しいことしか思い浮かばなかった。
まず、家族になることって大変なんですよね。
結婚して夫婦になることだって、育ってきた環境とか価値観の違いがあるから結構大変で、そこに子どもが生まれることも大変なことがあって、親と同居するにしても、これまたいろいろと大変なの。
家族というコミュニティをただやっていくだけでも大変なんだ。だからこそ、この詩を書いた子どもたちのように、問題を抱えてしまった子どもが出て来てしまうのもあるのだろうけど。
人と人が生きるって難しい。そう思ったのです。
社会性涵養プログラムについて、普通の子どもでも触れる機会があったなら社会はもっと優しくなれるんじゃないか
ここで書かれている社会性涵養プログラムはとても興味深く感じました。
これは、著者の方も書かれているけれど、問題を起こしてしまった子どもたちだけでなく、通常の学校教育の中に入れていったらずいぶん変わるんじゃなかろうか?と思った。
 学校の先生の意識も変わるだろうし、何より、これから社会をつくっていく子どもが変わっていく。
学校の先生の意識も変わるだろうし、何より、これから社会をつくっていく子どもが変わっていく。
それは、起こってくる犯罪や問題を未然に防ぐことにも繋がっていくのだろうし、もっとたくさんの人が暮らしやすい社会に変わっていくのではないかな?
きっと、このように犯罪を犯してしまう子だけでなく、ほかにも必要な人がたくさんいるんじゃないかなって思うの。
 どんなことも認め、褒められる。そういうの、必要だと思うんですよね。
どんなことも認め、褒められる。そういうの、必要だと思うんですよね。
学校で教わる、正しい文章や、正しいかたちの詩だけではなく、もっと自由に、もっと思うままに自分を表現できるようにすること。それを認められるようにすること。大切だと思う。
正しい形の文章でなくても、自分を表現することってとても大切だと思うし。
この詩の授業だけではなく、この社会性涵養プログラムの中身は良さそう。
私はこれを読んだだけでまだまだ全然詳しくないけれど。そして、社会に生きる人たちのほとんどが知らないことなのだろうけれど。逆に、だからこそ、もっと広まれば良いんじゃないのかな?と思うのです。
だって、それだけ必要で良いと思われているから実施されているのでしょ?
子どもが成長していく中で、「自分は愛されている」「自分は認められている」と感じることが心の成長につながるのだろうと思う
子どもが成長していく中で、どうしても欠かせないものがあるんです。
「子どもは勝手に育つ」なんて言葉はあるけれど、例えば身体が育つためには食べ物から摂取する栄養が必要なわけで、完全に勝手に育つことなんてありえない。
食べ物から摂取する栄養は、成長するためだけでなく、生きるためにも必要なもの。
 そう言った生きるため、成長のために必要なものって身体のための影響だけじゃなくて、心のためのもの、知識のためのものなどもあると思うんですね。
そう言った生きるため、成長のために必要なものって身体のための影響だけじゃなくて、心のためのもの、知識のためのものなどもあると思うんですね。
それらが全部そろっている状態で、人って人として安定していられる。そう思うのですよ。
それで、心のために必要なものが、「自分は愛されているんだ」って思えることとか、「自分は認められているんだ」って心から思えることなんだろうと、そう思うんですね。
それらは結局は、自分で自分のことを認めていく力に変えていくためのものなんだと思っています。
この本の中の中で特に印象に残っているのが、とにかくみんなで認めるっていうところで、それって本当に大切なことだと思うんですね。
「あぁ、自分は認められている」そう感じられることが子どもの心の成長を促すんだと思う。
この詩集の中に、好きな色というタイトルの詩があるんですが、ただただ直球に自分の好きな色が書かれているんです。
「好きな色は○○です」という感じで。
こういうの、大人が見たらなんて言いますか?あるいは学校でただ好きな色だけ並べてある詩が出て来たら、先生はなんて言うだろう?
たぶん、なんですけどね。
「ダメだし」すると思うんです。
「もっとこんな風に書こう」とか「もっとこういうことを書かないとダメ」とか。
正しさを教えようとするあまりに、「それで良いよ」って認めたりする前に「もっとこうしないと」って言っちゃうんですよね。
 「もっとこうじゃないと」「もっとこうしたら」もっと…もっと…
「もっとこうじゃないと」「もっとこうしたら」もっと…もっと…
言ってる側は本人がもっと伸びるようにって、相手のために…って思っているんだけど、それって本当に言われた子どものためになっているのかなって思うんですよ。
本当に、確実にその子のためになっているかなんて言う確証なく、ただ自分の自己満足で言ってしまってるんじゃないのかなって。
本当の本当の、奥底にあるものを覗いてみたときに、必要だったのってダメ出しじゃなくて「それ、良いね」とか「本当だね」って言うような認める言葉なんじゃない?って、そう思えて仕方ない。
「正しいものをつくれるようになるためのダメ出し」よりも「承認の言葉」や「褒められること」の方が欲しいんじゃないのかな?
「認めてもらえた!」「褒めてもらえた!」という思いが、「もっと書きたい」「もっとやってみたい」という気持ちにつながって、それから、正しい書き方とかを教えたら良いんじゃないかと思うんです。
社会のルールとか、人に対する接し方であれば、間違っているものは間違っていると伝える必要はあろうかと思うんです。
だけれど、文章とか、詩とか、美術というような芸術的なものなんて、正しさよりも、いかに楽しく自分を表現できるかの方が大切なんじゃないかなって思うんですよね。
だからそこで正しさを教え込もうとするよりも、「認められてうれしい!」「褒めてもらえてうれしい!」「もっとやってみたい!!」を育てるようなほうが良いんじゃないって思う。特に小学校とかね。
もっと心を豊かにすることを優先しながら、学校で実施する教育を進めていくことができれば、もっと子どもの心は成長しやすくなり、心豊かな人に育っていけるんじゃないだろうかと思うんです。
ダメだししすぎなんじゃないのかな?
犯罪を犯してしまった子どもたちは社会の被害者とも考えられるから、だからもっと広がって社会後と変えていければ良い
この著書に書かれていた、「犯罪を犯してしまった子どもたちは社会の被害者とも考えられる」というのは、本当にその通りだと思ったんです。
だからこそ、もっと広がればもっと変えていけるんじゃないかな?
最近の世の中はちょっとしたことをものすごく批判するなって思うんですね。私もそう言うところあるのかもしれないけれど。
とはいえ、人間なんて、…いえ、機械でも動物でも、なんか間違えたり失敗したりって絶対に出てくると思うんですよ。
機械は間違えない?そんなことないですよね。不具合とか故障だってある。絶対ってないんですね。
それをね、一度の過ちをいつまでも永遠に続くかのように責め続けたりするのっておかしいと思うんですね。子どもがやってしまったこととか、いつまでも責めるのってどうなんだろう?
犯した過ちは消えなくても、人は変わっていくもので、過ちを背負って心を痛めているのは本人であって、ほかの人は周りから批判するばかりってどうなの?
反省して更生して、生きていくことを当事者以外の人はもっと認められるようになったら良い。
それに、そもそもそうなってしまう前に、子どもが成長する段階でもっと心の成長が促せるような社会であれば良い。
親や学校の先生など、子どもと関わる立場にある大人が、もっとたくさんの知識をもって子どもの心が豊かにしていくことができるような、そんな仕組みが出来上がっていけば良いのにな…と、そう思ったのでした。
この本について気になった人は読んでみてください。
それでは、土出麻美でした。
 またね。
またね。