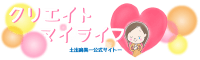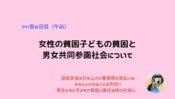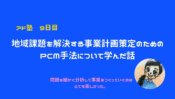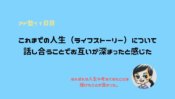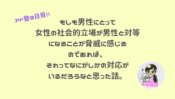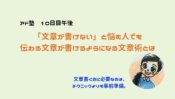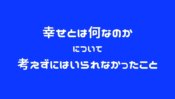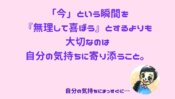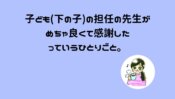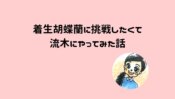男性介護社会と男女共同参画について考えた(アド塾5日目午後)
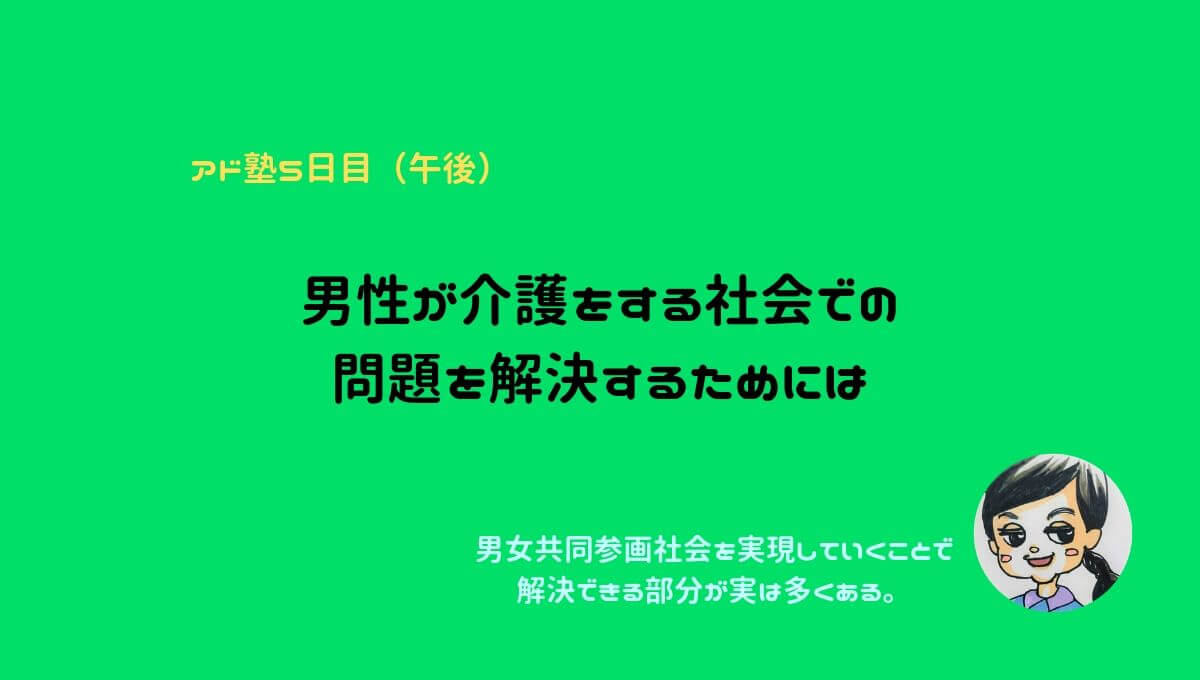
アド塾(男女共同参画アドバイザー養成塾)5日目の午後の講座は男性介護についての講座でした。
この講座を受けて考えたことは、昔は介護をする人といえば女性だったものが男性がする必要が出てきたということで、まさに男女共同参画社会が必要であるということができるということだということです。
これまでの性別で役割を決めてしまっている状態では回らないことがどんどん多くなっている…。
だからこそ、男女関係なく、社会の役割を均等に担う、男女共同参画社会を進めていく必要がある。そう言い切ることができるのです。
これまでの、男性が一日中、長時間仕事をしているというシステムのままではあらゆることが滞ってしまう。
そう考えたのでした。
今回の記事は、アド塾5日目の午後の講座をもとに、男女共同参画の視点を取り入れて紹介していきたいと思います。
この記事の目次
男性が介護をしなければ介護の担い手がいない時代の到来と男女共同参画
男女共同参画アドバイザー養成塾(アド塾)の5日目午後の講座は男性が介護の担う社会についての講座でした。(2019年7月13日、第9回目講座)
ただ、この講座は、どちらかというと介護をしなければならなくなった男性…つまり当事者向けの講座内容であったかな?と感じましたので、そこから考えた、男性介護と男女共同参画社会という視点で、私が実際に土遭遇した事例も交えながら書き進めたいと思っています。
男性が介護を担わなければならない時代がやってきたことでの問題点とは
少子高齢化時代と言われてずいぶんとなったのではないでしょうか?
内閣府の平成30年版高齢社会白書によると、平成29年10月1日時点での全人口のうち65歳以上の人口が占める割合は27.7%です。
つまり、約3割が高齢者です。人が10人いたら、3人ぐらいが高齢者。
29年の介護が必要な人の数は出ていないのですが、27年のデータで65歳以上のうち要介護や要支援の認定を受けている人の割合は約5分の1。
実際はもっといるでしょう。要介護認定は申請をしないと受けられませんので、要介護認定を受けない人もいますからね。
事実、「本人が嫌がるから…」という理由で認定を受けていない人は結構たくさんいます。
介護が必要である人が増えることで、これまで女性が担うことが多かった介護を男性がしなければらなないようになることが増えています。
結婚していない息子が介護をする。夫婦のうち女性が介護が必要になって夫が介護をするなど。
男性が介護をしないといけないという状況は大きく二つの問題が上がってきます。
た
- それまで家事もしたことがないので、家事や人の世話の仕方がわからない。
- 介護のために急に仕事を辞める必要に迫られる。
この二つの問題点について詳しく見ていきます。
これまで家事をしたことがなく、家事も介護もやりかたがわからない
多くの男性(特に年齢の高い層)は家事の経験がありません。家事は女性がするものだというのが醸成気だと思って育った世代です。(若くてもこういう人はまだいるのかもしれませんね。)
つまり、自分で家事ができない。家事のやり方どころか、どこに何があるかすらわからない。
やかんを火にかけたけど紅茶のありかがわからないような人が、紅茶のありかどころか、家事や自人の世話までしないといけなくなった…という状況です。
介護といえば、日ごろ家事をしている女性でも戸惑うことが多くあるもので、実際私が相談員として施設で働いていたころも、「どうしたらいいのか…」と涙されていた女性もいるほど。
そんなことを、何がどこにあるかさえわからないような人が急にしなければならなくなるのですから、それは大変です。
私も相談員の現役時代にあった事例では、母親の介護を一人されている男性、何を食べさせたら良いかわからず悩んだ末に、「刺身なら柔らかい」と考えて、毎日ご飯と刺身をなんとか食べさせていた、と話されていました。
介護のために急に仕事を辞める必要に迫られる
介護のために仕事を続けておくことができなくなることがあります。これは男性に限ったことではなく女性もあることですが。
問題に感じられるのは、これまでは介護といえば女性が担うものとされていたので、男性が介護を理由に仕事ができなくなるということを会社が想定していないからです。
講座の中での話では、近年、働き盛りで仕事がどんどんできていた男性が、会社に理由を言わずに退職してしまって、実はその理由は実は介護のためだったということが多くあるという話でした。
つまり、男性が介護をしなくならなければならなくなった場合、自分が「介護をしなければならなくなって仕事ができないということを職場に相談することができない」ということができますね。
女性が介護をしなければならなくなった場合よりも、より一人で抱え込みがちであると考えることができます。
この問題は非常に増えてきていて経済情報誌で特集として取り上げられるようになってきているとのことでした。
私も現役時代に「介護のために仕事を辞めて、貯金を切り崩しながら何とか生活しているけど、いつまでもこんな生活はできない」という事例がありました。
 その方も、私は相談員だからそういった話をすぐに話すことができていましたが、会社にはそんな話ができずにいたのかもしれませんね。
その方も、私は相談員だからそういった話をすぐに話すことができていましたが、会社にはそんな話ができずにいたのかもしれませんね。
二つの問題をまとめると
二つの問題をまとめると、これまで家事や自分の身の回りのこともしたことがなかった人が、急に自分の身の回りのことを含めた家事と人の世話までしないといけなくなって、誰に相談することもできず、介護をするようになっているという状況がうかがえますね。
場合によったら離職を選ばざるを得なくなっている。
まったくやったことがなくて、やり方も知識もないことをしないといけなくなった…。
その状況を例えると、これまで海は見たことあったけどボートを漕いだりしたことなかった人が海のど真ん中で一人、手漕ぎのボートで浮かんでいるような感じでしょう。
だんだん介護の必要度があがっていくので、仕事と両立ができなくなり、一人悩んで離職を選択する…。という状況ですね。
介護をする必要が出てきた男性が抱える問題を解決できるのが男女共同参画社会
介護をしなければならなくなった男性が抱える問題の原因が何かを考えたときに、それを解決する方法は、まさに男女共同社会の実現であるということができます。
男性が直面した問題は、そのほとんどが男女で役割を分けていたことによって起こっているからです。
これまで家事をしたことがなかった理由は?
家事は女性がするものだとされていたからですね。これが、「家事は女性」ではなく男女どちらもが担うべき仕事であると認識されていたならば、まったく家事をしたことがなかったとなる可能性は低くなります。
どこに何があるかわからないのも、それまで自分の身の回りのことまでもやってもらって当たり前だったからです。
家事だけでなく、子育てや介護も男女が共にかかわっているのが当たり前のことであれば、これほど困らなかったことです。
離職問題についても同じように男女共同参画社会であれば解決することができるでしょう。
介護は女性が担うものであるという認識が広く浸透しているから、介護をしないといけなくなった男性が「介護で…」と会社に言い出すことができない現状になっているのです。
そして、会社のシステムが、「家事や育児、介護は女性が担うもので男性はしなくて良い」という前提で作られているから、両立ができないような勤務体制になっているのです。
家事や育児、介護を誰もが担うべきであるとなっているのであれば、おのずと仕事と両立ができるシステムにせざるを得ません。
最初から仕事をしながら家事育児、介護も両立できるシステムであれば、介護を担う必要性が出てきたからと言って急に離職を考えなければならないようにはなりませんね。
もともとのシステムが男女共同参画になっていないからこれらの問題が出てきていて、それに悩んだ男性が一人で悩んで離職を選ぶようになっているのが現実でしょう。
介護サービスを利用すれば離職しなくて済むのか?
「介護サービスを使えば離職しなくて済むだろう」と考える人もいるかもしれませんが、そううまくいくことはまれであるといえます。
実際は、どうしても介護保険内では回らなくて、費用を自己負担でサービスを利用しなければならなかったり、もしくは、言い方は悪いかもしれないけどほったらかし状態になってしまっていたりするのが現実だと考えて間違いではないでしょうね。
好きでほったらかしにしているのではなくて、そうでないと回らない…というのが本音だと思います。
どちらかを犠牲にしないと生活自体が回らないので困っている人も多いと思います。
だからこそ、どちらも両立できるようなシステムに変えていく必要があるのです。
男女共同参画社会を実現させることは、これらの問題を解決させていくための基本的な考え方ということができます。
男性が介護をしなければならない社会だからこそ、男女共同参画社会の実現が必要
高齢者の数が圧倒的に多い社会になりました。
これからはこれまでと同じ社会システムのままでは日常生活を送ることができなくなっていきます。
これまでは介護は女性が担っていましたが、男性が配偶者の女性を介護したり、息子が母親の介護をしなければならないようになりました。
これまで家事をしたことがなかった男性は、急に家事と介護をしなければいけなくなり、何をどうしたらよいかわからないようになっています。
仕事と介護の両立ができなくなって、会社に介護のことを伝えることなく急に離職することも増えています。
このような男性が一人で悩むことになっている問題を解決できるのが男女共同参画社会の実現です。
男女が共に仕事も家事育児や介護を担うのが当たり前である社会にすることで、急な家事に悩まされることも激減し、家庭と仕事の両立が可能なシステムに変えていくことができるからです。
今回の講義を受けて男女共同参画社会を進めることが男女ともに生きやすい社会にすることができると確信することができました。
それでは。
土出麻美でした。